
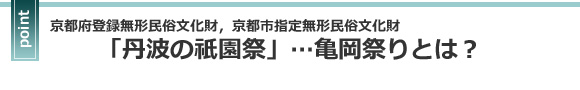 毎年京都府亀岡市で開催される「亀岡祭」は、鍬山神社の鍬山宮・八幡宮二社の例祭です。 11基の山鉾が巡行する様子から”丹波の祇園祭”とも呼ばれ親しまれています。 今年も10月23日から25日までの3日間行われる「山鉾行事」を中心に、亀岡祭の詳細をご案内します。 |

|
 |
|
10月01日 氏子領境八箇所御斎榊立て/吉符入り -鍬山神社 10月05日 くじ取り式 -亀岡市役所市民ホール  10月18日 御神輿飾り -鍬山神社  10月18日 神幸祭(おいで祭り) -形原神社  10月23日 【宵々山】山鉾ライトアップ&夜店  10月24日 【宵山】山鉾ライトアップ&夜店  10月25日 【本祭】旧城下町一帯を山鉾巡行  10月26日 御神輿仕舞い -鍬山神社  10月31日 神事済奉告祭 -鍬山神社  |
|
 |
|
 |
北町「鍬山鉾」
 丹波の開拓神「鍬山大明神」をご神体とした舁山です。 現在伝承されている懸装品の大半は、文化8年(1811年)に新調されたもので、特に胴掛幕の「黄羅紗地西洋花文様捺染」は、イギリスのヴィクトリア朝時代の毛織物で、東インド会社による交易でもたらされたものです。当時の町衆の国際性や心意気を感じさせられます。 平成14年、約200年ぶりに囃子の一部が復活しましたが、15年には全7曲が完成しました。 平成17年、200余年ぶりに曳山(鉾車をつけ)に復元新調を果たし、城下町特有の狭い曲がりくねった道に対応する仕掛け(からくり)もついて、巡行に雄姿をお見せします。 |
 |
西町「八幡山鉾」
 氏神である鍬山神社には、丹波開拓の神である大己貴神(大国主神)と、祭神である誉田別尊(別名・八幡神)の二神をお祀りしています。 八幡山鉾は名前のとおり、八幡宮を御神体とし、亀岡祭山鉾11基中、唯一造営記録が残されています。 その『八幡山記』には、「宝暦十三年(1763年、今から約230年前)九月新たに山を造営して八幡山号し奉る。」とあり、舁山として造営されました。 また、天保12年(1841年)には、現在の曳山に改装されました。 それ以来、先人の貴重な遺産を守るため、これまでに幾度となく小修理を重ねてきました。 平成3年からは、町内住民に修復基金を募り、京都府・亀岡市・亀岡地区財産区のご協力により、平成の大修復をおこないました。 |
 |
紺屋町「武内山鉾」
 神功皇后が宇佐宮で安産された応神天皇を、武内宿称が抱いた姿をご神体としてお祀りしています。 この山鉾の造営年代は、胴幕の箱銘から、安永6年(1777年)頃と考えられます。 山鉾を飾る懸装品のうち、文化4年(1807年)に百人講合力により新調された見送り幕は、中国清朝の皇族クラスが使用するような優品です。 さらに、鉾の欄縁の箱銘には、"文政12年(1829年)新調、蟷螂山町"とあることから、祇園祭山鉾の旧材が用いられたことを知ることができます。 なお、昭和52年にいち早く「武内山囃子方保存会」を結成して、囃子の保存継承、技術の向上に努めています。 |
 |
本町「三輪山鉾」
 大和の国三輪山麓に鎮座する大神神社の祭神である「大物主大神(おおものぬしのおおかみ)をご神体とし、能楽「三輪」の後シテの女神像で表しています。 「古来一社の神秘なり」として、三輪山の大神神社に現存する三ツ鳥居は、全国鳥居多くあれどこの形式は唯一無二のものです。 本町三輪山鉾の正面には、澄みきった心身で神に近づく意で、この三ツ鳥居が神門として飾られています。 亀岡祭は、戦後しばらく中断していましたが、昭和28年ごろに復活し三輪山鉾だけが町内の巡行を続けました。 鉾町民の維持、保存継承にかける心意気と未来に向けた不断の努力を、この囃子の音色に感じていただけたらと思います。 |
 |
柳町「高砂山鉾」
 謡曲「高砂」の「尉」と「姥」をご神体としている高砂山は、人形道具箱の銘によると、 宝暦5年(1755年)頃に舁き山として建造され、文政8年(1825年)に現在の曳き山に改修されました。 見送り、水引、前掛幕は、この時に新調されました。 見送り幕は、西陣で製作された大型の綴錦で、当時最も高価な織物であり、往時の町衆の祭りにかける熱意の程を今に伝えています。 また、蝶や蝙蝠等をあしらった幾何学模様の絨毯地の胴幕は、敦煌等の仏教遺跡で知られる中国甘粛省で織られた毛織物であり、異国の風を感じさせます。 |
 |
塩屋町「蛭子山」
 釣り上げた大きな鯛を抱いてニッコリと笑った恵比寿像をご神体とする蛭子山は、旧胴幕に転用された水引幕の銘文から、 寛延四年(1751年)ごろに建造されたと考えられています。現在、伝承されている縣装品は、下水引が明和六年(1769年)、 前掛幕・胴幕等は天保二年(1832年)に新調されました。 蛭子山の自慢は西陣大型綴の見送幕です。三人のオランダ人を描いたこの綴織りは、鎖国の時代にあって、 外国の風景を題材にした風流の趣の最高潮に達した姿です。 このように、亀岡祭山鉾では、当時の織物のなかでも制作費の一番高い大型綴錦を11枚も揃えており、 祇園祭を除く、他地方の追随を許さない町衆の心意気を表しています。 |
 |
矢田町・京町・上矢田町「難波山鉾」
 百済国から渡来した漢の高祖の子孫と伝える「王仁」をご神体としています。 この王仁は、『論語』10巻、『千字文』1巻を伝来した人物です。 難波山鉾は、欄縁の箱銘から、安永6年(1777年)頃に舁山として建造されたとされます。 また、『引山記』によると、寛政11年(1799年)に曳山として現在の鉾の姿に改装されました。 この改装に際しては、町衆が10年間祝儀、不祝儀、諸普請を問わず、質素倹約に努めることを申し合わせ、経費を捻出したとあります。 文末に、「町中が、えいやえいやと、引山に、なおすも神のちからなりけり」とあるように、町衆の結束の強さを伝えています。 |
 |
新町・旅籠町「稲荷山」
 稲穂を天秤棒で背負う「稲荷神の倉稲魂」をご神体として祀っています。 山の造営時期は、装束箱の銘により寛延4年(1751年)と考えられています。 文久3年(1863年)に新調された旧前懸幕の「浅葱地雲龍文様繻珍綿」は、中国清朝の皇族が使用するような優品とされています。 現在の前懸けは、平成11年に復元新調されました。 胴幕は、朝鮮李朝の毛綴を立継ぎにして使用し、見送り幕には、京都西陣で織られた「虎に仙人図」の大型綴錦で飾るその姿は、 風流山の完成された姿であり、祇園祭をのぞく、他地方の山懸装の追随をみないものです。 また、世話役が纏っている渋染半纏は江戸時代より着用していた装束です。総指揮用の黒半纏を宵々山、宵宮で展示します。 |
 |
呉服町「浦島山」
 釣竿を手にした浦島太郎をご神体とする浦島山は、天明7年(1787年)の行列帳に記載され、この頃に建造されました。 浦島山の天水引は、中国清朝の皇族クラスの官服原反を水引に仕立てたもので、中国から樺太経由で松前藩にもたらされた蝦夷錦と呼ばれる高級錦です。 この水引は、京都に出て成功した熊野忠兵衛が、見送り幕とともに寛政11年に寄付したものです。 また亀岡祭では、祇園祭に次いで朝鮮毛綴を多用しますが、そのほとんどは裁断して縦継ぎにしています。 そのなかで、浦島山の胴幕は「玉取り獅子」文様で完全な織物の状態で伝来する貴重なものです。 山飾りがしばらく途絶え、会所での部屋飾りとなっていた浦島山が、平成5年、町民の熱い想いと結束により復活し、現在に至っています。 |
 |
西竪町・東竪町「羽衣山鉾」
 謡曲「羽衣」の天女の舞姿と漁夫をご神体とする山鉾です。 建造当初は曳山として、亀岡祭山鉾のなかでも最も大きな規模を誇っていたとされ、天明5年(1785年)の行列帳にも記録が残っています。 その後老朽により、一昨年までは西竪町と東竪町との輪番で飾り山となっていましたが、平成11年には、地元町衆の熱意によりお囃子方が復活しました。 さらに平成14年、山鉾復元の声が高まり、130年ぶりの復元、新調をはたしました。 ご神体として天女と漁夫が祀られ、その大きさは資料に基づき、各山鉾の中でも最大となっています。 また、山鉾の廻りを彩る懸装品はすべて町衆の手作りによるものです。 |
 |
三宅町「翁山鉾」
 能楽で祝に演じられる「式三番」に由来し、白色尉と黒色尉の面が伝わっています。 「式三番」が能楽の催しの最初に演じられることから、この翁山も宝暦の末までは、巡行に際して籤取らずで先頭を巡行していました。 しかし、一時途絶え、文政12年(1829年)に再興されました。 再興に際しては、いずれも西陣の大型綴錦で、前懸幕は三国志の主人公、 劉備・関羽・張飛を描いた「桃園の結義」、見送幕は「鳳凰額八仙人図」を新調しています。 翁山鉾の何よりの特徴は、大きな車輪です。直径145cmの車輪をきしませて、一番長距離の巡行となります。 |
| →亀岡祭山鉾連合会HPより引用させて頂きました。 |